第1回 孔子のキャリア形成
本と風景あるいは、本のある風景というようなスタンスで、これからしばらく筆をすすめてみたい。どのような内容での展開になるか自分でもわからないが、単なる本の紹介でなく、著者との出会い、その人となり、ちょっとしたエピソードなどにも触れられればと思う。“本”はあるいは“絵”に替わることもあるだろうことを、あらかじめお知らせしておきたい。
最初にとりあげるのは、孔子の対話録である『論語』である。いまことさら論語ブームというわけでもないが、かといって多くの人にとって関心の薄い「過去」の読みものというのでもなかろう。修身だ道徳だと世の中が「右傾化」するとき、引っ張り出されることが多かったとの印象は、拭いがたいかも。率直に読めばなかなかいい本だ、というような気持ちで宣伝するつもりもない。
孔子は、いまを去ること約2500年前(紀元前500年)、中国は魯(山東省)に生まれた思想家である。文学をもふくめて中国文明の創始者である。紀元前500年前後には、ギリシアでは、ソクラテス、ヘラクレイトス、アイスキュロス、ヘロドトスなどがインドでは釈迦が生まれている。東西の巨人が期せずして生を受けた時期である。これは単なる偶然なのだろうかそれとも…と考えると、孔子の言う“学び”の世界に一歩ちかづく。
子曰、学而時習之、不亦説乎。有朋自遠方来、不亦楽乎。
人不知而不慍、不乎君子乎。
子曰く、学んで時に之を習う、亦た説ばしからず乎。朋有り遠方自り来たる、亦た楽しからず乎。人知らずして慍らず、亦た君子ならず乎。
おおくの人が中学、高校時代に目にしただろう、開巻「学而第一」冒頭の言葉である。
先生は言われた。「学んだことをしかるべきときに復習するのは、喜ばしいことではないか。
勉強仲間が遠方から来てくれるのは、楽しいことではないか。人から認められなくとも腹をたてない。それこそ君子ではないか。」
『論語入門』(岩波新書)で井波律子さんは、このように訳している。「学」のうちには古典を学ぶことのほか、儀式や日常生活における礼法を実践的に学ぶことも含まれるとも。
『論語』は、顔回、子貢、子路をはじめとする弟子たちとの対話を記録したものであり、中国でもっとも広くかつ長く読まれてきた書物である。日本には『古事記』に百済からもたらされたと記されているという。以後、千年以上にわたり読みつがれ、江戸時代には武士をはじめ、寺子屋を通じ庶民にも広く浸透した。
孔子は下級武士の生まれで家は貧しかったが、勉強家であった。30歳のころには学問の基礎ができあがり、弟子もふえた。仁愛と礼法を中心とした儒家思想の骨格もほぼできあがった。みずからの思想を実践に移そうと政治への参加を志すが、下剋上の嵐にみまわれた時代であり、成果はあがらなかった。ばかりか、失敗、失脚の連続であった。生命の危機に直面したことも再三であった。しかし理想社会の到来を期して弟子たちを励まし、不屈の精神力をもって仕事をもとめ、長い旅をつづけた。いかなる不遇のどん底にあっても、ユーモア感覚を失わず、学問や音楽を心から愛し、日常生活においても美意識を発揮するなど、生きることを楽しむ人だった。
子日、朝聞道、夕死可矣。(子日く、朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり。)
子日、不患人之不己知、患不知人也。(子日く、人の己を知らざるを患えず、人を知らざるを患うる也。)
『論語』をつらぬいて流れるものは、ふてぶてしいまでの人間肯定の精神、人間の善意への信頼である。孔子の教えがいまの世の教えとして不適当なところがあるとすれば、それはあまりにも厳格な教えであるためでなく、むしろあまりにも人間を肯定した楽観的な教えであることである。こうした楽観を成り立たせるもの、それは人間の能力、善意に対する信頼であった。(吉川幸次郎『中国の知恵』筑摩書房)
子日、吾十有五而志于学。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。
七十而従心所欲、不踰短。(子日く、吾れ十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従って、矩を踰えず。)
先生は言われた。「私は十五歳になったとき、学問をしようと決心し、三十歳になったとき、学問的に自立した。四十歳になると、自信ができて迷わなくなり、五十歳になると、天が自分に与えた使命をさとった。六十歳になると、自分と異なる意見を聞いても反発しなくなり、七十歳になると、欲望のままに行動しても、人としての規範をはずれることはなくなった。」(井波律子訳)
私がいつもそばにおいて見る『論語』(中央公論、世界の名著3、昭和48年、26版)の著者である貝塚茂樹先生は、万事控えめで、非常に反省心が強く、自己を誇らない孔子が、いつも苦難に満ち、試練にさらされて成長してきたその生涯を無限の感慨をもってふりかったことばである、と指摘する。
いま日本では、国を挙げてキャリアパスとか、キャリア形成についてかまびすしい。人はいろいろな仕事を通じて技量をみがき、知識を獲得し、家族を維持して自分の生涯をまっとうするしかない。孔子の屈託のない生き方は、勇気も与えてくれる。

清水 皓毅(しみず・こうき)
株式会社エイデル研究所 主幹
福祉経営研修センター 常務理事
北海道生まれ。中央大学経済学部卒業、産業経済関係の出版社を経てエイデル研究所設立に参画。賃金、労務管理、人
事管理等のコンサルティング、各種調査の企画実行担当。
社会福祉分野では、全社協「福祉サービス従事者の標準研修プログラム検討委員会」、同「市区町村社会福祉協議会管理職員研修カリキュラム検討委員会」、同「ボランティアコーディネーター研修プログラム研究委員会」など、福祉人材の養成研修に関する各種委員会に参画。
全国社会福祉協議会をはじめ、各都道府県社会福祉協議会および福祉施設の経営者研修などの指導、講演に従事。


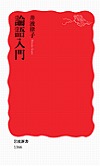

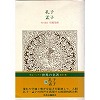
 TOP
TOP