第3回 佐藤忠良が“彫り刻んだ”もの
宮城県美術館の佐藤忠良記念館にはじめて行ったのは、2007年11月4日だった。くもり模様の日ですこし寒かったが、市内バスでむかった。ちょうど「日展100年」という大きな催しものの最終日にあたっていた。そちらの会場はかなり混雑していたが、佐藤記念館は人影もまばらで見るには具合がよかった。
展示室5には、母の顔(1942)、オリエ(1949)、木曽(1955)、常盤の大工(1956)など比較的初期の作品があり、なじみに逢う心地よさがあった。展示室6には、あぐら(1972)、裸のリン(1977)、若い女(1971)など、展示室7には、いわゆる“小児科”の作品、展示室8には、ボタン(1969)、帽子・夏(1972)、記録をつくった男の顔(1978)などの代表作があった。
佐藤はなぜ人体というか人間の像にこだわるのかを、この日も反芻したが、解答は見出せないままに外にでることになった。作品の前に立つとそのような設問がじつはまったく意味を失ってしまう。ほかに替えることのできないもの(おおきな存在)の前で、ひとはなにを求めようとするのか。沈黙をこそ―――。
 1981年フランスの国立ロダン美術館で2か月にわたり開催された佐藤忠良の作品展は、予想を上回る評価をうけ、日本の具象彫刻のレベルの高さをつよく印象づけるものとなった。この時出品された「母の顔」への評判は、佐藤本人にもおどろきを与えた。同展開催のために佐藤のアトリエにきた女性美術館長ローランは、作品をつぶさにみてまわったとき“これも出品してください”と指名したのが「母の顔」だった。美校を出て間もないころの作品だったので断ったのだが、どうしても出品してほしいといわれ出すことにしたという。“するとおかしなもので、その展覧会では他のどの作品よりも、その「母の顔」の評判がいいんですね”(『彫刻の〈職人〉佐藤忠良』、2003年、草の根出版会)。新聞や雑誌、週刊誌にのり、紹介、批評記事もたくさん出た。
1981年フランスの国立ロダン美術館で2か月にわたり開催された佐藤忠良の作品展は、予想を上回る評価をうけ、日本の具象彫刻のレベルの高さをつよく印象づけるものとなった。この時出品された「母の顔」への評判は、佐藤本人にもおどろきを与えた。同展開催のために佐藤のアトリエにきた女性美術館長ローランは、作品をつぶさにみてまわったとき“これも出品してください”と指名したのが「母の顔」だった。美校を出て間もないころの作品だったので断ったのだが、どうしても出品してほしいといわれ出すことにしたという。“するとおかしなもので、その展覧会では他のどの作品よりも、その「母の顔」の評判がいいんですね”(『彫刻の〈職人〉佐藤忠良』、2003年、草の根出版会)。新聞や雑誌、週刊誌にのり、紹介、批評記事もたくさん出た。
「佐藤忠良はポーズの独創性、物質主義に汚染されていない作品の輝きを増しつつ、ロダン、ブールデル、マイヨールの純粋に西洋的な線や動きを捉える術を心得ている。彼の作品は物質主義の害を受けずに20世紀に生きる。… 佐藤忠良は、まず物と個人を尊重する。彼のアプローチが誠実で熱のこもった人間性に満ち満ちたものであることは、彼が伝統の中に改革すべきものを求めることの妨げにはならなかった。」(クロード・パレー)
2011年2月4日、私は世田谷美術館に『ある造形作家の足跡 佐藤忠良展』を見に出かけた。往きは成城学園前駅からのバス、帰りは千歳船橋駅行のバスだったが、帰りのほうが歩きもすくなくスムーズだったことを記憶している。この美術館との相性がいまいちと感ずるのは、行くたびに雨模様になるからだ。性懲りもなく足をはこぶのは、その日の展示物を拝見する目的のほかにもうひとつ、いつみても美しい砧公園の喬木に逢えるからだ。
この日もやはりくもりだった。会場は混んでいた。そうだろう、もうすぐ白寿をむかえようとする人の、彫刻87点、素描72点、絵本・挿絵原画79点、さらに美術教科書などを展示する“回顧展”をファンは待っていたに相違ない。
挿絵原画『ビーバーの星』の少年と鹿の闘いの数葉に衝撃をうけた。ウルトラマリンとセルリアンブルーのアンサンブルで画面全体を構成した藍の世界、その大胆な構図と色彩に一歩もひけをとらない筆さばきで、躍動する動物と人間の格闘。そして細部に宿るリアリズム。水彩、鉛筆、パステル、墨でこれだけの作品ができあがるのだ!圧倒的な芸の力というしかない。
年譜をみているとシベリア抑留の前後に目がむかう。1940(昭和15)年吉田照と結婚し、翌41年達郎、43年オリエが誕生する。44年7月32歳で応召。満州のソ連、朝鮮国境近くに配属される。45年ソ連軍に投降。その後3年間シベリアの収容所に抑留される。48(昭和23)年夏、舞鶴港に帰還、4年ぶりの日本。「シベリアに連れて行かれたという、一般にはあまり味わえないような、稀有な体験をしたなら、制作して発表するものが大きく変わる人がいます。ところが私は、作品に取組む態度は、兵隊にいく前とちっとも変らないんです。」ただ、捕虜という身になり決められた膨大な労働を毎日、黙々とこなしていかなければならない生活を通して見えてきたものがあった。それは学者や社長などという肩書や地位のある人よりも、「農民や大工さんや商人というふつうの人たちのほうが信頼もできるし、親しくもなれることが実感的にわかった」からだという。(『彫刻の〈職人〉佐藤忠良』)
多くの芸術家がそうであったように、佐藤は世に出るまでに尋常ならざる苦労をしている。作品が売れるようになるまで“50年はかかったな”。それまでは水面下に足場としての石を積み上げるだけだった。50年も積み続けて、やっと水面に顔をだしたのだ。シベリアでの苦労を尋ねたとき、佐藤は“彫刻家になるための苦労を思えば、あんなものは何でもありません”と答えたと、安野光雅は日経新聞の追悼文で言っている。
さまざまなジャンルを平然と超えて仕事をする佐藤の作品群は、見るものの背中をおすというかやわらげる。どのような見方、考え方をしても許されるような気になるからだ。作者の意図はこう、この作品に込めたものはこうという押し付けがない。どうぞいつまでも作品のまえで会話してください……。
この会場に佐藤本人はついに姿を見せることはできなかった。会期は3月6日までだったが、それから2旬日あまりの30日に彼はもうひとつの世界に逝ってしまったのである。
98歳であった。

清水 皓毅(しみず・こうき)
株式会社エイデル研究所 主幹
福祉経営研修センター 常務理事
北海道生まれ。中央大学経済学部卒業、産業経済関係の出版社を経てエイデル研究所設立に参画。賃金、労務管理、人
事管理等のコンサルティング、各種調査の企画実行担当。
社会福祉分野では、全社協「福祉サービス従事者の標準研修プログラム検討委員会」、同「市区町村社会福祉協議会管理職員研修カリキュラム検討委員会」、同「ボランティアコーディネーター研修プログラム研究委員会」など、福祉人材の養成研修に関する各種委員会に参画。
全国社会福祉協議会をはじめ、各都道府県社会福祉協議会および福祉施設の経営者研修などの指導、講演に従事。


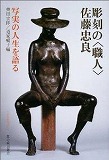
 TOP
TOP